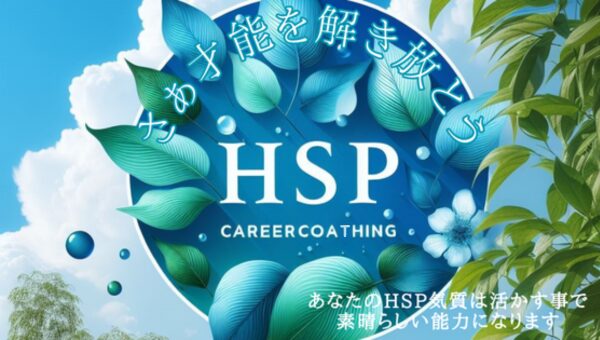現代社会では、うつ病や不安障害、統合失調症など、さまざまな精神疾患を抱える方が増えています。
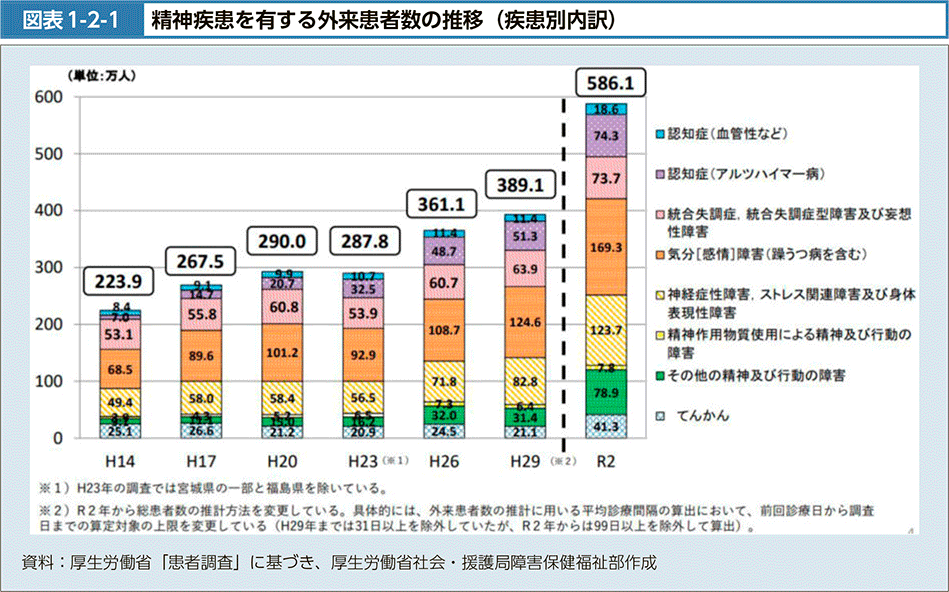
そして、近年増えているのが「本人や家族だけではケアが難しい…」「どう接すればいいかわからない」というサポートする家族側の悩みです。
そんな悩みに寄り添う選択肢の一つが「訪問看護」。プロの看護師がご自宅へ伺い、専門的な視点で日常生活や心のケアをサポートするサービスが広まりつつあります。
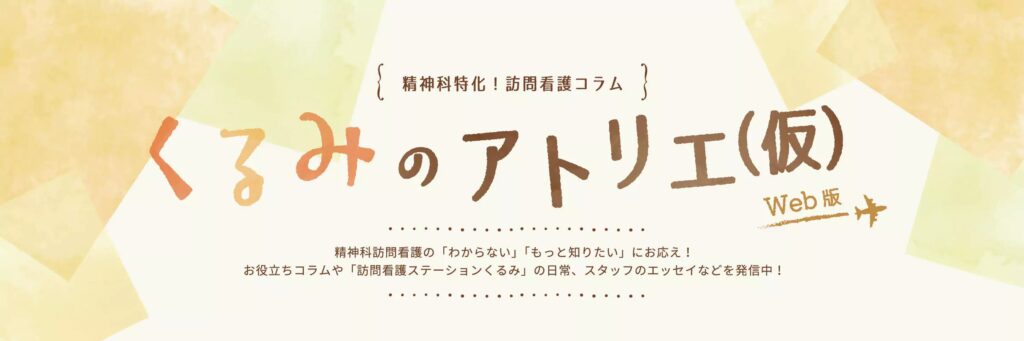
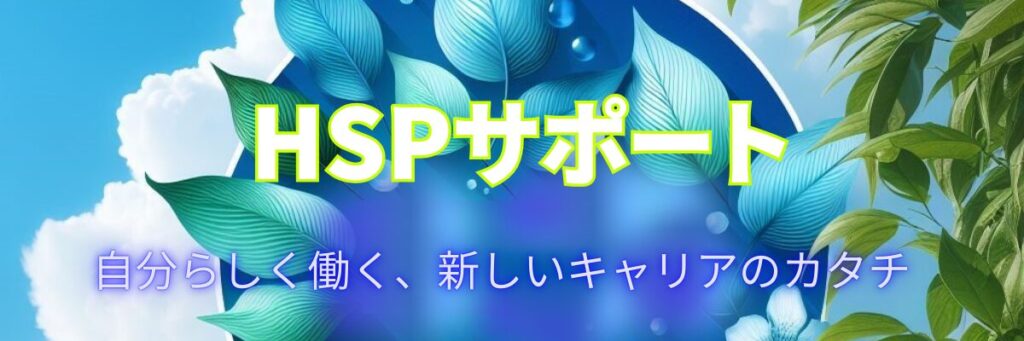
精神疾患患者と暮らしの悩み
心に病を持つ患者に対しての接し方は、患者の症状や行動にどう対応して良いか分からず戸惑うことが多く、当事者にとってはどう家族に接するかを悩むケースが多くあります。
また、精神疾患は目に見えにくいため、家族間や周囲の理解が得られにくく、「こんなことで相談していいのか」「迷惑なのでは」と感じて孤立しやすい状況に陥ることもあります。患者本人も心身の辛さを上手く伝えられず、家族がサポートに悩む場面が少なくありません。

さらに、家族が一人で介護や見守りを続けてしまうと大きな負担となり、共倒れになるリスクも高まります。
そのため、家族全体で役割を分担したり、専門機関への相談や外部サービスの利用が推奨されています。精神疾患患者がより自分らしく生活できるためにも、家族と支援者が協力しあい、安心できる環境を整えることが大切です。
訪問看護とは?
一般的に訪問看護とは、訪問看護とは、看護師や理学療法士、作業療法士などの医療専門職が利用者の自宅を訪問し、健康状態のチェックや医療処置、生活支援を行うサービスです。
医師の指示に基づいて提供され、自宅で安心して療養生活を続けられるようにサポートします。
精神疾患患者が利用する時の特徴やメリット
精神疾患の方が訪問看護を利用する利点は、自宅という安心できる環境で専門的なケアを受けられる点です。
病院とは異なり、個別の状況に合わせた丁寧な寄り添いが可能で、症状の悪化予防や生活リズムの維持を支援します。定期的な訪問により継続的なケアが受けられ、社会復帰や生活技能の向上につながる支援も期待できます。
くるみのアトリエの訪問看護サービス内容
- バイタルサイン(血圧、脈拍、体温など)の測定や体調の観察
- 服薬管理・服薬指導:薬の飲み忘れを防ぎ、副作用などの対応もサポート
- 問診による精神的な状態の確認、不安や悩みの相談対応
- 日常生活の困りごとや生活リズムの調整支援
- 利用者の「こころのかたち」に寄り添った丁寧な傾聴と支援
- 地域の医療機関や保健・福祉サービスとの連携体制を整備
- ご本人だけでなく、ご家族の相談支援やサポートも実施
利用者が住み慣れた場所で安心して療養や回復を続けられるよう、多面的な支援を届けています。
ご本人だけでなく家族もサポート対象に
訪問看護は、患者本人だけでなく、介護や支援を担う家族に対しても相談や指導を行います。
「介護疲れ」というワードを耳にしたことがある方も多いですが、この言葉は老人介護だけでなく精神介護も含まれています。実際、家庭内で精神的ケアが続くと、家族が肉体的にも精神的にも疲弊し、悩みや不安、本音を抱えてしまう場面が多くなります。
例えば、親族のケースで妻に先立たれた叔父がいました。その際、同居家族の疲れや、看病を続ける中での不安を間近で感じました。「このままでは共倒れかもしれない」と心配になるほどでした。

ある日、叔父が体調を崩し入院したことをきっかけに介護保険が適用され、訪問介護が導入されました。プロの視点から丁寧な相談と提案を受けたことで、家族の不安や負担が軽減し、叔父の症状は安定。今では親族にも笑顔が戻りました。
9月には介護認定4から介護認定1になりました👏
この様に、訪問介護には家族の不安や負担を軽減し、適切なケアが継続できるようチームとして支える体制が整っています。これにより、ご家庭全体が精神疾患の影響を最小限に抑え、安心して生活できる環境づくりができるのです。
まとめ
精神科訪問看護という選択肢は、本人だけでなく家族や周囲の人にも大きな安心と支えをもたらします。自宅という生活の場で、生活やこころの困りごとを相談できる存在がいることで、家族も患者も「自分らしい暮らし」を取り戻していくきっかけとなります。
くるみのアトリエは、精神科訪問看護の専門家として、利用者の「こころのかたち」に寄り添う支援を日々届けています。看護師がご自宅に伺い、体調や薬の管理、不安や悩みのケア、生活リズムの調整まで幅広く対応。
家族の不安や疑問についても丁寧に相談を受け、継続ケアの中で暮らし全体をサポートします。

自分や家族のメンタルケアについて悩みや疑問があれば、ぜひ一度「くるみのアトリエ」の公式サイトを覗いてみてください。サービス内容や利用方法、相談・問い合わせもわかりやすく紹介されています。
【公式サイト】https://kurumi.makecare.co.jp/
※専門スタッフが個別相談を受け付けているので、まずは気軽に相談してみるのがおすすめです。